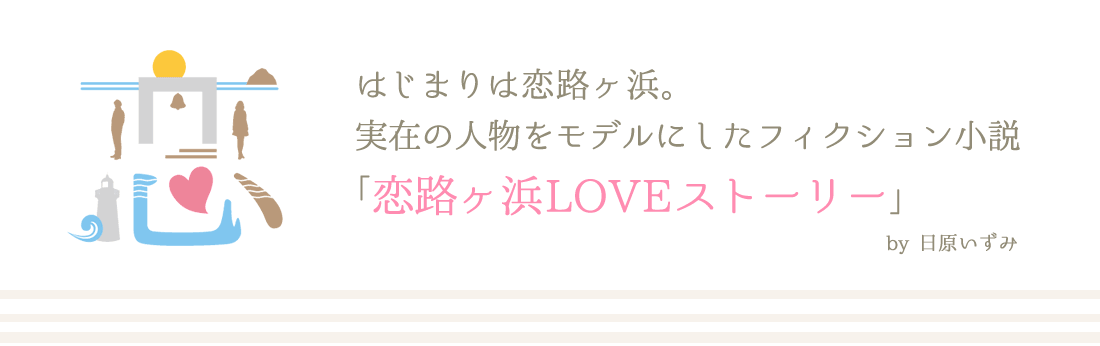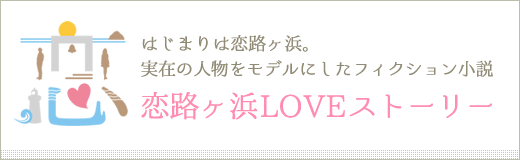野菜の苗を植えながら土のにおいに包まれた。
息を吸い込むと、懐かしい気持ちになる。
幼い頃にも泥遊びや砂遊びをした記憶はあるが、土のにおいは憶えていない。
東京の土に、においはあっただろうか。
それなのに、懐かしさを感じているのはなぜだろう。
ぼくが今感じているこの懐かしさは、ぼくの体験した記憶ではない気がする。
生まれる前から知っているDNAに刻まれた記憶・・・。
 ぼくは、東京の設計事務所で働いていた。
ぼくは、東京の設計事務所で働いていた。
勤めて4年目のある頃から、会社へ行けなくなった。
確かに仕事は忙しかったが、特に不満があるわけではなかった。
仕事はおもしろいし、会社仲間にも、友達にも恵まれている。
でも、急に泣き出したり、電車に乗れないという、自分でも驚くような状況が訪れ、
病院へ行ってみたら、抑うつ状態だと診断された。
休職していた2ヶ月の間に東日本大震災が起きた。
東京も大きく揺れた。福島で原発事故も起こった。
今思えば、3.11も転機のひとつとなったのかもしれない。
4月に職場に復帰したものの、漠然と田舎暮らしをしたいと思うようになった。
インターネットで見つけた「新農業フェア」に出かけ、農業の「の」の字も知らず、土いじりをしたこともなく、虫だって嫌いなのに、
その世界に飛び込んでみたいと思った。
調べると、農業は人手不足で、農業法人の人員募集もあれば、国や県の支援も充実している。
それなりの倍率や面接をくぐり抜け、二つ示された候補のうち、ぼくが選んだのは、
愛知県渥美半島にある「Happinessあつみ」という農業体験施設だった。
風に吹かれたたんぽぽの綿毛がふわりと舞い降りるように、
10月、ぼくは縁もゆかりもなかった渥美半島に一人でやってきた。
家を出て暮らすのは初めてのことで、母親はぼくの体調を心配した。
クリニックで出してもらっていた薬はちょうど終わりの時を迎え、調子は悪くなかった。
何より、田舎へ行けば、健康になれるんじゃないかと思った。
農業研修生として住み込みさせてもらえるので、引越しの荷物に家具はいらず、
身の回りの衣類や生活用品を詰め込んで、車で移動することにした。
渥美半島では車は必需品らしい。
出発は深夜にした。両親と弟が見送ってくれた。
研修期間はまず5ヶ月の予定なので、少し長い旅に出るような気持ちだった。
夜のうちに高速を駆け抜け、浜松インターを降りて、浜名バイパスを走る。左手に海が見えてきたが、まだ暗い、夜の海だった。
でも、張り詰めていた空気がゆるんだ気がする。
国道42号線に入り、渥美半島を目指す。
午前5時。
空が少しずつ明るくなってきた。
Happinessあつみは、渥美半島の中ほどにあり、施設長のヒロさんは、「朝、何時でもいいよ」と言ってくれていたけど、
さすがに早いと思い、ぼくは渥美半島の先端の伊良湖岬までそのまま車を走らせることにした。
車はほとんど走っておらず、時々トラックとすれ違った。
海が近づいてきた頃、ぼくは車を停めて外の音を聴いてみた。
木々の向こう側から、ザザーン…ザザーンと確かに波の音がする。と同時に、潮の香りが車内を満たした。
友達と思い立って湘南や房総の海に行ったことは何度かあったが、波打つ海というのは、なぜこうも気持ちが高ぶるのだろう。
ワクワクしてきた。
ぼくはさらに車を走らせ、白んできた空と追いかけっこするように、岬を目指した。日の出を浜辺で迎えたい!
左手にゴツゴツした大きな岩が見え、それがどうやら「日出の石門」のようだった。その駐車場を見送り、さらに先を目指す。
小山のような道を空に向かうようにしてぐんぐん登っていくと、眼下に海がばーんと広がった。
空が白み始めた海は青みを増して、ぼくは地球の上に確かに乗っかっていると思った。前方には伊良湖岬の先端が見える。
写真や映像で見たことのある広大な海と砂浜と緑の景色だった。
感動したまま車を走らせ、たどり着いた駐車場に車を停めて、浜辺に急ぐ。
さっき通った日出の石門の背後の空がどんどん色を変えていき、水平線を黄金色に染めたかと思うと、ぷくっと丸い太陽が顔を出した。
 太陽は目の覚めるようなオレンジ色で、線香花火の玉にも似ている。
太陽は目の覚めるようなオレンジ色で、線香花火の玉にも似ている。
その玉がどんどん昇って大きくなり、輪郭をくっきりさせていくと同時に光の強さを増していく。
その間、空は、雲のかかり方によって、黄金色や茜色に変化し、空自体の青色を濃くしていった。海はずっとその変化を静かに映し出している。
ぼくはこの先の渥美半島での暮らしを、日の出によって祝福してもらっているように感じた。
なんて美しいんだろう。
圧倒的な光景に包まれて、自分がまるでロードムービーの主人公になったような気分だ。
自然が織りなす美しい色に自分まで染まったような気になりながら、ふらふら歩いていると、浜辺で何かを拾っているおじいさんに出会った。
「日の出、素晴らしいですね」
思わずそう話しかけると、おじいさんは、
「そうだら~」と、誇らしそうに立ち上がる。
「天気や雲の具合によって、空の色も太陽の色も海の色も全然違うだよ。毎日見とっても飽きんね」
おじいさんは、浜辺のゴミを集めているようだった。
「ここは、恋路ヶ浜って言うらしいですね」
「そうだよ。いい名前だら。大昔から恋にまつわる色んな言い伝えがあったそうだよ。
<春さめにぬれてひろはんいらご崎 恋路ヶ浦の恋わすれ貝>っていう和歌や、
高貴な男女が、ゆるされん恋ゆえに都から逃れて、この地で仲睦まじく暮らしたとか、
時の関白が伊良湖の庄屋の娘と恋に落ち、この浜で優雅な恋の語らいをしたとか、色々由来があるだよ」
「そうなんですか」
 おじいさんは、これまでに何度も同じ説明をしてきた様子で、慣れたように言葉を重ねる。
おじいさんは、これまでに何度も同じ説明をしてきた様子で、慣れたように言葉を重ねる。
ふるさとに誇りを持っているのがわかる。
「男はミル貝に、女は女貝になって、三河湾側と太平洋側で別れて暮らしたという説もあれば、
この恋路ヶ浜で男女が一緒に桜貝になったという説もあるよ」
と、おじいさんは、ニヤリと笑った。
ぼくは、大昔から繰り返されてきた美しい日の出の風景や、この浜を歩いたという男女の姿を想像しようとしたけれど、目の前の、たった今の美しい海を見ているだけで胸がいっぱいになった。